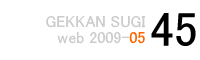また暫くすると篠原教授から再度、ご連絡を戴いた。
「『日向本』のとりまとめを手伝って欲しい!」
すぐに研究室に伺うと、先生はニコニコしながら云われた。
「黒澤明監督の『七人の侍』みたい、日向のまちづくりのために野武士どもが一人また一人と加わっていく風な構成にしたいんだ!」
早速、「七人の侍(黒澤明監督)」のシナリオ本をamazonで探し出し、先生へお送りした。
黒澤明のシナリオは、細かく場面説明されている訳ではないのに、シーンが浮かんでくる。
当初は「日向市駅から」という仮タイトルのシナリオの冒頭は、藤村さんと正一さんの車中での会話だった(新日向市駅・第二幕)。
「スーツ姿のオジサン二人が、狭い車中でお互いに難しい顔をしてボソボソと何やら交渉している・・・。」
そんなシーンがイメージできた。
まちづくりやデザインの現場の最初から最後までが、こんな風に読み手に伝わるとしたら、凄いことだと思った。
これまでの本には、結果は描かれているが、そのプロセス・葛藤が描かれることはなかったからだ。
しかし現場の最前線に立っている人たちは、実はその苦しい部分をどうやって超えるかを知りたいのだ。
それからは、とにかく夢中だった。
本来業務の合間を縫って、どんどん増えていく原稿を夜中に整理するのは、とても楽しい時間だった。
集まってきた原稿を幕ごとに組み直して、シナリオ風に整理し、その原稿をまた皆さんへ送って細かな点を確認してもらい、さらに篠原先生に校正して戴く。何度もそんなやり取りが続き、送る原稿もどんどん厚くなっていった。
中村さんとは、ほぼ毎日、互い原稿をチェックし合い、それはまるでプロジェクト最中のやりとりの再現のようだった。
また、このプロジェクトの全貌を把握していると思っていたのに、細かなことになると、間違っていた記憶や初めて知る裏話、描けることや描けないことなどが、次々と現れてきた。
皆さんが大変気遣ってくださったが、この作業を辛いと思ったことなど一度もなかった。
むしろ皆さんの生原稿に最初に触れられる喜びの方がずっと大きかった。読むたびにドキドキした。
この作業だけに没頭できたら、どんなに幸せかとも感じていた。
そうして季節は、あっという間に春から夏を過ぎ、いつしか秋が近づいていた。
今回、「本の編集」という作業に携わる機会を得て、つくづく思ったのは、
このプロジェクトに関わってきた人たちの「絆の強さ」だった。
業種も立場も年齢も異なるのに、原稿やデータ、写真をお願いすると皆さん、すぐに対応してくれる。
久しくお会いしていない人への原稿依頼も二つ返事で引き受け、アイデアも出してくれる。
日向プロジェクトでの「絆」が脈々とつながっているからだ。
篠原先生の「本」にしたい熱い想いをみんなが理解しているからだ。
おそらく、この本を読んで頂いたスギダラ仲間の方々が共感される部分だと思う。
日向プロジェクトは、今でこそ多方面から評価されているが、その最中は暗闇のトンネルの中で、みんな必死に出口の明かりを探し求めていた。その苦しさを共有してこそ生まれた「絆」なのだ。
また、この作業を通じて、改めて多くの方々とゆっくりこのプロジェクトを振り返る「時間」も戴いた。
実は余り向き合って話したことのなかった正一さんや津高さん、永崎さんともお話しできた。
この「絆」と「時間」は、ボクの財産だと思った。
こうして積み重ねられた、みんなの約十年の歴史を綴るシナリオは、7月にはたった17頁だった原稿が、11月には180頁にまで膨れ上がっていた。 |