 |
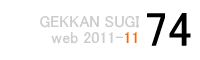 |
|
||||||||||||||||
| それでは、始めましょう!まず最初に、私が目にした、家々のアプローチや構え、風景の全体像をご紹介します。前半は「じょうぼ」の風景、後半は「谷津・民家・蔵・寺」の風景となっています。じっくりとご覧下さい。 | ||||||||||||||||
| ■じょうぼの風景 | ||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 「じょうぼ」とは | ||||||||||||||||
| ●彰国社の建築大事典によれば 「城ぼ」=関東地方の民家において、門などを構えないで塀や垣根をあけているだけの屋敷入り 口。「じょう」は入り口の意。とある。 |
||||||||||||||||
| ●城郭や豪族屋敷の研究をされている九十九里総合研究所の伊藤一男氏によれば、 「城圃(じょうほ)」=門前の小圃(しょうほ) 「小圃(しょうほ)」=門前を飾るお花畑 =門畠(かどはた) 江戸時代、武士の備えとして、矢来の組める空間、戦争になった場合は臨時の防壁を設けるこ とのできる空間(武者溜まり)を維持するため、平時には畑もしくは花畑、植え込みとして門 前を飾る空間とするのが「じょうほ」。武士の真似をするのが一種のステータスだったから、農 民の間にも広がり、方言やなまりで「じょうぼ」となったのではないか。と予想されている。 |
||||||||||||||||
| ● 沖縄の方言について書かれた伊波普猷全集 第4巻によれば じょう=門・門前の道路・門前通り・往来道から宅地内の門までの小径 じょうぐち・じょうのくち=道路の口・大通りへの出口 「じょーくち」「じょうぐち」の分布 :青森・山形・神奈川・静岡・新潟・鳥取 「じょーぼー」の分布 :千葉 千葉県香取郡 →ぢゃうぼう=宅地へ出入りする路 千葉県夷隅郡 →じょーぐち=家の入口 →じょーぼう=屋敷の入口 |
||||||||||||||||
| ●じょうぼ と 長屋門 について 曲線を描くアプローチの他に、長屋門を持つアプローチが多く見られます。 長屋門は武家由来と言われているのですが、農村に何故ここまで長屋門スタイルが多いのか、 農村と武家スタイルの関係性について調査当時より疑問に思っていたのですが、つい先日、大 分県は杵築で武家屋敷を改めて見る機会があり、これらの長屋門と母屋からなる屋敷配置が、 武家形式そのものであることが分かりました。 そこで改めて千葉県の歴史をひもといてみますと、千葉県は上総の国・下総の国に別れるので すが、その全域に渡って武士の集団を形成していた時代も有ったと言うことを知り、農村に武 家屋敷スタイルが多くあることに納得したのでした。 |
||||||||||||||||
| 第1回 その2へ続く | ||||||||||||||||
●<おおつぼ・かずろう> 建築家 |
||||||||||||||||
Copyright(C)
2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |
|||