 |
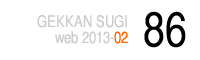 |
|
||||||||||||||||
| team Timbeizeでは、 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| を合言葉に、木を新しい建築材料ととらえ直して、木造建築を都市木造として再認識をすることを試みてきた。 | ||||||||||||||||
日本では古くから木材を使って建築をつくってきており、法隆寺に代表される伝統木造建築は日本の誇るべき文化であることは間違いないが、木造建築の可能性はそれだけではない。 |
||||||||||||||||
| 建築は、それが建てられた時代の社会システム、要求によって変化していくものである。現在、求められる木造建築は、特に、都市部についてみれば伝統木造建築とは全く異なるものであることは疑いない。近代以降、鉄やコンクリート、プラスチックに置き換えられてしまった「木」を新しい材料として、今もう一度、建築の世界に用いていく必要があるのである。 | ||||||||||||||||
これまでも、「工学的木造」「新興木構造」「新木造」など新しい木造建築を生み出す試みは、繰り返し行われてきた。 |
||||||||||||||||
| 木というと英語で<wood>がすぐに思いつきますが、丸太は<log>、人の手によって加工された材木とか製材は<timber>となる。Timberize(ティンバライズ)は、この「timber」から考え出された造語であり、固有名詞というよりは、「木」を新しい材料としてとらえ、木造建築の新しい可能性を探っていく合言葉と位置付けている。 | ||||||||||||||||
2009年12月、駒場にある東京大学生産技術研究所のくうかん実験棟にて『都市の木造建築展』を開催した。多くの一般の方にご来場いただき、中高層木造建築の実現性について、広く認識してもらうきっかけとなった。その一方で、来場者の意見から、建築模型による展示は、木造空間の魅力を伝えるためには十分でないことを知らされることになる。木造空間の魅力は、その存在感、手触り、香りといったさまざまな要素を伴って感じられるものであることが再認識された。 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| 『都市の木造建築展』2009年12月、東京大学生産技術研究所のくうかん実験棟にて。 | ||||||||||||||||
| そこで、より現実の都市木造の空間を体験することを目指して、2010年5月に表参道のスパイラルで、『ティンバライズ建築展 - 都市木造のフロンティア』を開催した。この展覧会では、「木・木材の祭り」を合言葉に、木と木造の良さはもちろん、建築・家具を中心に「木を使っていろいろなことができる!」「都市の中だって、木造の建築が建てられる!」というメッセージを、五感で感じてもらえるように実大の展示物を作成した。東京の中心部の表参道を舞台に、都市木造プロジェクトを提案。今までにない、都市における木造建築のドローイングやスケッチ、模型や映像を通して、都市の新しい木造建築=『都市木造』とはどのようなものか、その可能性と実現性に迫った。 | ||||||||||||||||
また、木・木造に関する最新の情報や技術の紹介、さらに都市木造の実物大モデルや特徴的な木質材料を用いた家具によって、会場を『ティンバライズ』することで、皆様に木・木造の実際の大きさや肌触り、色や匂いを体感できるようにした。現代建築の象徴的なスパイラル(設計:槇文彦)の中での、木造空間はより象徴的に表現することができた。 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| 『ティンバライズ建築展 - 都市木造のフロンティア』2010年5月、表参道 スパイラルにて。 | ||||||||||||||||
| 展覧会はその後、2010年7月「静岡展」、10月「なごや展」、2011年7月「北海道展」と巡回してきた。それぞれの展覧会では、新たな都市木造を体験することを主にしながらも、各地で独自のテーマも掲げてきた。 | ||||||||||||||||
「静岡展」では、これから都市木造を体験する子供向けに木に接することを、「なごや展」では、都市木造を生み出すための地方自治体、公共建築の役割を、「北海道展」では、これから社会にでて都市木造を設計する若手建築家、建築系学生による札幌市内での都市木造の提案をテーマにしてきた。 |
||||||||||||||||
 |
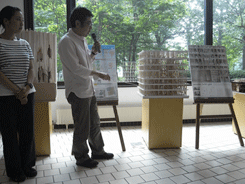 |
|||||||||||||||
| 「静岡展」2010年7月 | 「北海道展」2011年7月 | |||||||||||||||
そして2012年11月の「九州展」では、建築系学生による博多市内での都市木造の提案とともに、プロダクトを含めた都市での木材の活用をテーマに展覧会を企画した。九州という森林資源が豊かな地域で、木に関わる関係者は建築業界に限らず多岐にわたる。 |
||||||||||||||||
| その筋で有名なスギダラとの連携、「スギダライズ」、「ティンバラケ」の実現、さまざまな分野で、さまざまなかたちで木が使用されることで、都市の中でも木に接する機会が増えることになれば、その価値を各自が認識できるようになるはずである。当然、木に対する価値観は、それぞれの人で異なっていてもよい。 | ||||||||||||||||
展覧会を通じて学んだ「木の存在感」、巡回展が都市木造の実現と、木を再認識するきっかけになればと期待している。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Copyright(C)
2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |
|||