 |
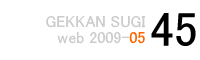 |
|
||||||||||||
● |
||||||||||||
今年の桜は早咲きだったせいか、いつにもまして美しく感じられた。こんなにもじっくりと、そしてこれまでと異なる視点で桜を見たのは初めての経験だった。同じ風景なのに違う感じ方をするようになったのかも知れない。たとえば、満開の桜が咲く様は、空間というキャンバスに絵を描くようにも見える。あるいは、花が開く直前は、指先で触れるだけで“ポン”と音を立てて花が開くのではないかと思うほどだ。いかにも初々しい。やがて花は競うように全体が薄紅色の空間へと変貌していく。 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
● |
||||||||||||
| |
花は、散るときもまた画になる。ハラハラと散り尽くす様は、思わずじっと見入ってしまう。一気に咲き誇り、一時の栄華を誇らしげに見せた後、惜しげもなく散り行くさまは、ひとりの日本人として、ただただ美しいと感じる。そして桜の花びらは、時として二度目の花を咲かせる。それは、選ばれし時と空間と、そこに居合わせた偶然とが、地面に描かれる絶妙の点描画をさらに際立たせる。 こうした桜の季節を、人々は祝い、祈った。「神が長くそこにとどまるように」と。桜には神が降り立つと信じられてきた。 |
|||||||||||
 |
||||||||||||
● |
||||||||||||
スギもまた、注連縄を張って神を祠る。天にまっすぐに向かうその姿は、年月を経るほどに信仰の対象としてふさわしい。 |
||||||||||||
● |
||||||||||||
スギは日本の文化の外郭を形作ってきたようにも見える。あえていうならば、ここまで日本人に使われながら、愛着もなく放置され、また、見捨てられた材料も珍しかろう。写真は、廃屋ではあるが、港の潮風をいまだに受けつづけ、木はやせ細って筋が浮き上がっている。しかし、そうした厳しい自然条件の中で、建物の形を頑なに守ろうとしているようで、何ともいとおしい。 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
● |
||||||||||||
陰が、その年輪の一本いっぽんを刻む。なでると気持ちよさそうにカタカタと鳴く。軽くて乾いた声だ。年輪は、その数を増すことはやめてしまったが、「俺がこの風景を何十年とみてきたんだぞ」と言わんばかりの迫力も併せ持つ。 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
時おり、この木は動き回る。泳ぐといってもいいかもしれない。職人は、木の声を聞き取りながら、その曲(くせ)を知り尽くし、さも当然のように居場所を与える。時が過ぎ、住み手を失ってもなお、味わい深い、職人の“意気”を感じる。なんという大胆さ、それでいてなんと繊細なのだろう。 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
|
||||||||||||
 |
||||||||||||
● |
||||||||||||
|
||||||||||||
この春、日向の駅前に広場公園が完成を迎える。事業が始まって10年、構想からは数十年。広場には、桜があり、その脇をせせらぎが流れている。そして、芝生は市民の足を止める。
|
||||||||||||
 |
||||||||||||
●<いのうえ・やすし> |
||||||||||||
Copyright(C)
2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |
|||